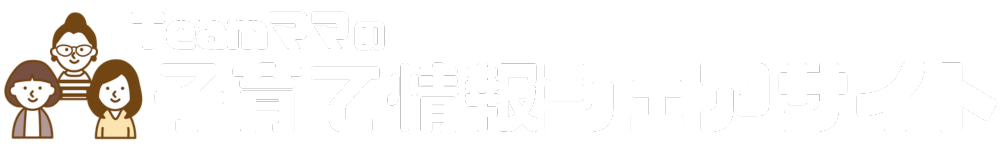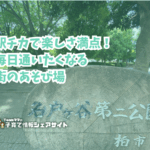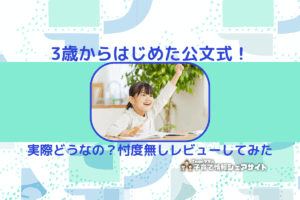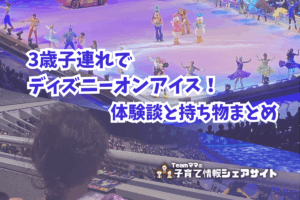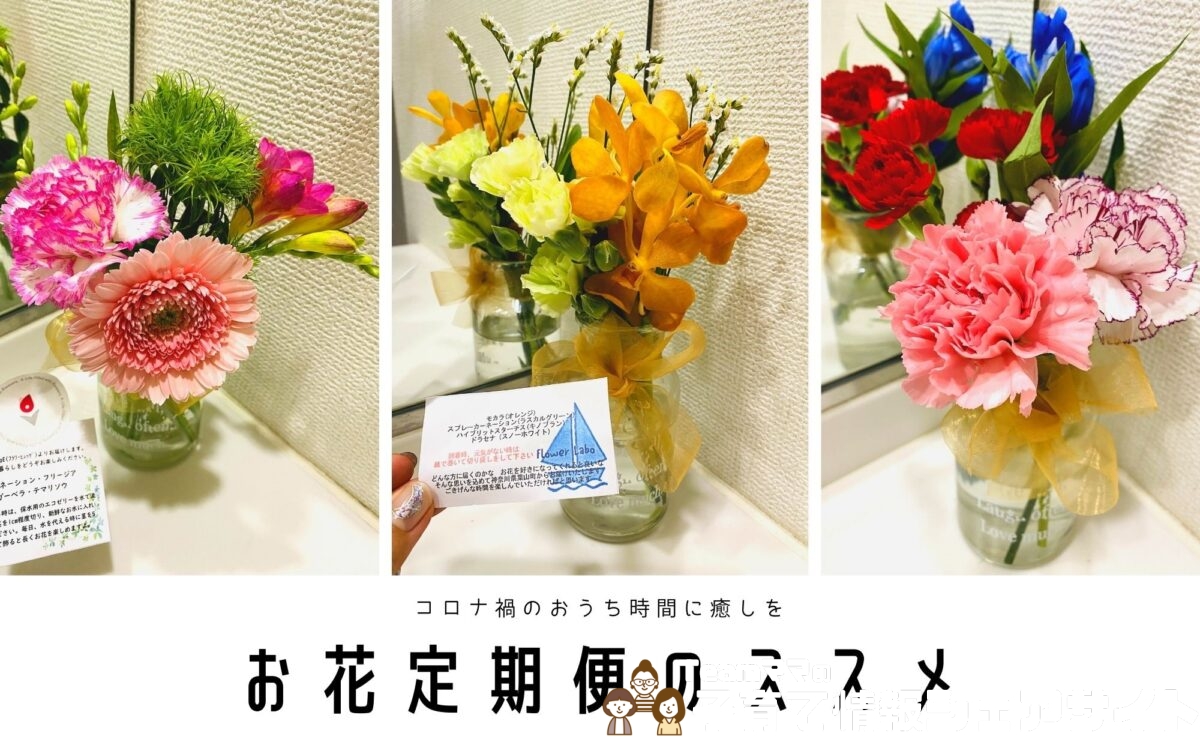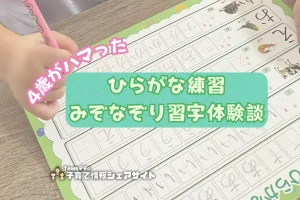現在、小学生の子ども2人を育てている主婦のtukkiです。今回は下の子が生後3ヶ月でRSウイルス感染症に罹患し、総合病院に5日間入院した時のことを母親としての目線で記していきたいと思います。2017年時点のことであり、今とは異なる部分も多々あるかと思いますが、どなたかの参考になれば幸いです。合わせて、万が一の子どもの入院に備えて必要なことも紹介しています。
目次
そもそもRSウイルス感染症って何?
RSウイルスの感染による呼吸器の感染症です。2歳までにほぼ100%の子どもがRSウイルスに少なくとも1度は感染すると言われており、1度かかると何回もかかります。症状は発熱、鼻水などの軽い風邪のような症状から重い肺炎まで人により度合いが大きく異なります。特に生後6ヶ月以内に感染した場合は重症化する場合が多いです。
始まりは上の子の軽い風邪から
我が家は、当時4歳であった上の子から生後3ヶ月の下の子にRSウイルス感染症がうつりました。上の子が発熱し、かかりつけ医を受診。軽い風邪とのことで、処方された薬ですぐに治りました。しかし数日後、下の子があまりにも元気がなかったため、熱を計ると38度以上の発熱があり、急遽かかりつけ医を受診。病院の先生曰く、生後6ヶ月以下の子が発熱することはほぼないとのこと。ウイルス感染もしくは重篤な病気が予想されるとのことで、ウイルス検査を行い、RSウイルス感染症にかかっていることが判明しました。合わせてパルスオキシメーターで血中酸素飽和濃度を計測すると、90%を切っており、慌てた様子のかかりつけ医から救急車で搬送される旨を伝えられ、酸素マスクが子どもにあてられました。平均的な酸素飽和濃度は96~99%。90%をきると呼吸不全であり、当時我が子はかなり危険な状態であったようです。急展開すぎて記憶があまり残っていないのですが、病院に近づいてくるサイレンの音は8年経った今でも耳に残っています。
上の子はどうしよう!?突然始まった入院生活
上の子が幼稚園に行っている時に入院が決定。息つく暇もなく、酸素マスクをあてられた子どもが救急車で総合病院に搬送され、治療が開始しました。治療は対処療法で、点滴による薬の投与がメインでした。夫は単身赴任中であり、完全なワンオペ育児だったため、上の子の面倒は全て実家にお願いする形で、下の子に24時間付き添う入院生活が始まりました。入院先である病院の小児科は、子どもが病室内に入ることが禁止であり、入院生活中に上の子と会えたのは1、2回で時間は合わせて30分ほどだったかと記憶しています。実家の両親の助けがなければどうなっていたか分かりません。
初めての付き添い入院生活、戸惑うことばかり
子どもの治療が第一で、病院は病人を治す場所であるため、当たり前のことですが、付き添い人のベッドはなく、ご飯もありません。大人用サイズのベッドで子どもに添い寝する形となりますが、生後3ヶ月だったこともあり、特に狭さは感じませんでした。ただ安全のための転落防止柵が周りを覆う形となるので、多少圧迫感を感じる場合もあるかもしれません。加えて完全母乳で育てていたため、私以外の人が世話することができなかったため、5日間の内誰かと交代してもらったのは、1回だけ。お風呂に入るために家に戻った時だけでした。食べ物は院内のコンビニで、子どもが寝ている合間に急いで買っていました。
安心感は計り知れないけど、気が休まらない
生後3ヶ月で、頻回な授乳が必要だったこともあり、私自身は朝昼夜と気が休まることはありませんでした。しかし病院にいると、毎日の検温や吸引、薬の確認など我が子の治療のために看護師さんや薬剤師さんが入れ代わり病室内に来てくださいます。命の危機にあった我が子を24時間体制で見守ってもらえる安心感は計り知れなく、入院生活においては感謝しかありません。
5日間の入院生活後、ようやく退院へ
病院の先生から退院の許可がおり、ようやく普通の生活に戻ることができました。医療従事者の方々には本当に感謝しかなく、入院生活自体も子どもが治ると思えば不便なことも全く嫌ではありませんでした。幸い私は実家に頼れる環境下にいましたが、そうでない場合に備えておくことも大事だなと強く感じました。
【万が一の子どもの入院に備えて、やっておくと良いこと】
✅最寄りにある総合病院の情報収集
→私は救急車で搬送時にどこの病院が良いか聞かれました。事前に把握して一覧にしておくと安心です。
✅住んでいる市町村の子育てサポート制度の確認
→市町村によってサポート制度は大きく異なります。こちらから働きかけ、役所と連携することが大事です。
✅医療費制度や加入している保険の医療補助が使用できるかの確認
→医療費の他に、別途個室代などがかかります。制度をうまく活用して少しでも負担が減る方法を探しました。
備えあれば憂いなし
子育ては未知のことの連続です。下の子で入院生活を経験するとは思わなかったですし、これからも予想外の出来事が起こることが考えられます。それが子育ての大変さかつ魅力でもあるのですが、いざという時に慌てないように、さまざまなことに備えていけたらと思っています。子育て情報の共有も大事な備えかと思うので、これからも私の情報を子育て中の皆さんとシェアしていけたら嬉しいです。